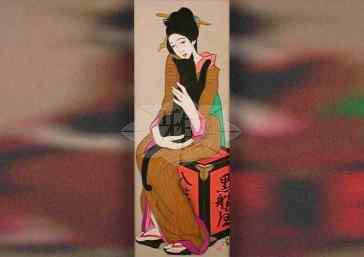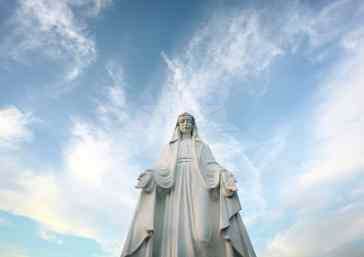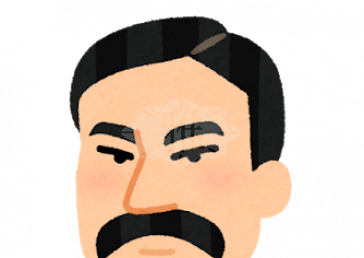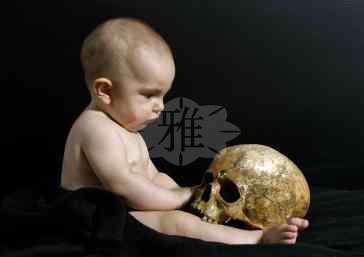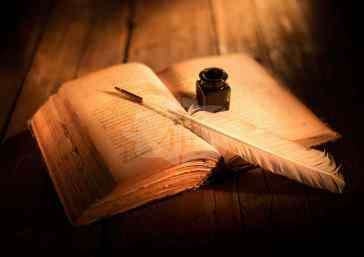イラスト:ノイズ喜久田友紀
江戸時代には、有名な遊女たちがいかに「いい女であるか」を示すための逸話を集めた「遊女評判記」というジャンルの書物がありました。日本広しといえども、徳川幕府から正式に営業を許された官許の色街といえば江戸吉原、京都島原、大坂新町という3つしか存在しなかった時代のお話です。 「遊女評判記」で描かれるのは、これらの3つの官許の色街が抱える数千人の遊女たちのうち、トップクラスの何名かの逸話だけでした。
しかし、彼女たちはみな貧しい田舎町の貧家から、親の借金のカタとして売られて来た身の上です。「遊女評判記」に逸話を残す名妓とはいえ、現代のわれわれが彼女たちの人生について知ることができるのはごく断片的な情報だけなのでした。
しかし、きわめて稀なケースではありますが、名妓(めいぎ)たちの中には年季中に亡くなった遊女であっても丁寧に埋葬され、立派な墓石も建ててもらい、長年にわたって丁寧に供養され続けた形跡がある女性がいるのです。
夕霧太夫が大阪の人々に愛された訳

西暦17世紀後半、寛文年間(1661-73)に、京都島原から大坂新町に移籍した記録を持つ夕霧は、それまで「三大遊郭」の一翼を担いつつも、島原に比べるとハイクラスな遊女がいないとされてきた大坂新町では珍しい「太夫(たゆう)」という称号の持ち主でした。
現代でも浄瑠璃の名人たちなどに受け継がれている「太夫」は、遊女の世界においても最高ランクの称号でした。
「太夫」は、「花魁」に比べると、あまり馴染み深い称号ではありませんが、かつては江戸吉原の遊女たちにも名乗られていたものの、その称号の遊女に見合う扱いや支払いができる客が時代を追うごとに減ってしまい、18世紀後半には絶滅したという経緯があります。ちなみに「花魁」は、「太夫」よりもグッと低めのランクの称号ですね。
夕霧太夫が京都から大坂まで船路でやってきた時には、彼女の姿をひと目見たいという人だかりができたとか……。
その後も夕霧太夫は、自分を強く慕う者であれば、魚屋、八百屋のご主人といったきわめて一般的な庶民であっても、直接会って、お話くらいはしてくれるフランクな人柄で人気を集めました。
井原西鶴の『好色一代男』にも夕霧太夫は登場し、「姿かたちはしとやかで肉づきよく、目つきは利口そう。声がよくて、肌の白さは雪」、そして「命とりの床上手」だったそうです(訳・吉行淳之介)。特筆すべきは「阿蘭陀人」のようなグレーがかった、もしくはブルーの瞳のミステリアスな美女だったことでしょうか。
豪商の息子との恋の結末は?

そんな彼女ですから、身請け――大金を払ってでも、自分の愛人、いや妻になってほしいと願う客は多かったのですが、夕霧は大坂の豪商の息子・伊左右衛門と熱愛関係にあり、彼から見受けを持ちかけられています。しかし、なんと夕霧は伊左右衛門の申し出をきっぱりと断ったのでした。
その経緯としては、自分に入れあげて親から勘当され、破産した伊左右衛門に胸を痛めていた夕霧の逸話が散見されます。
あるとき、ボロボロの格好で現れた伊左右衛門が涙を流しながら「今の自分に自由になるお金はこれしかない」といって、一文銭(現代では数十円ほどの価値)を懐から取り出すので、夕霧も泣きながら、それを押しいただくようにして受け取りました。
一日でも早く、早く借金を返させてやって、夕霧を自由の身の上にしたいという伊左右衛門の愛を感じたからでしょう。
しかしその4、5日後、伊左右衛門の使者が夕霧のもとを訪れました。そして使者から告げられたのが「伊左右衛門が夕霧を身請けしたいと願っている」という衝撃的な申し出だったのです。事情を聞けば、あれはすべて夕霧の愛を試すための芝居で、伊左右衛門はすでに親から許され、裕福な身分に戻っていたのだとか。
夕霧は、自分の真意を信じてくれなかった伊左右衛門に愛想を尽かし、「あなたに身請けしてもらうことはできない」と丁寧な言葉ながら、申し出を断ったのです。
夕霧の墓石を煎じて飲む?

そして延宝6年(1678年)1月7日、22歳とも27歳ともいわれる若さで大坂新町の置屋・扇屋の遊女として病没したのでした。記録には残っていませんが、葬儀も立派だったのではないでしょうか。
慶安元年(1648年)に大坂町奉行所が「町人作法」と呼ばれるお触れを出しており、そこには「金銀を散りばめた美麗な葬礼を禁止する」とあります。しかし、この命令を守る者は少なかったようですね。有名人ともなれば、白昼堂々、立派な葬列が街中を練り歩き、多くの人たちが見物に訪れる現象が見受けられました。
大坂中の人々が夕霧の若すぎる死を悲しみ、彼女の墓は扇屋の主人たちの菩提寺であった浄国寺(現在の大阪市天王寺区)に建てられました。伝説の遊女・夕霧を慕う人々は、彼女の死後も多く、いつしか「夕霧の墓石を煎じて飲めば、病気が治る」という言い伝えが広まったため、文久3年(1863年)には新しい墓石に交換せねばならなくなったという逸話もあります。