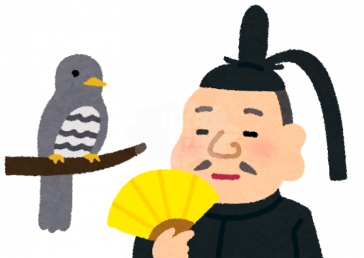在原業平

在原業平 「つひに行く 道とはかねて聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを」
父母はそれぞれ親王・内親王という、貴族社会のサラブレッドに生まれながら、政治的には不遇だった在原業平。
見目麗しい外見と華麗な恋愛遍歴、そして思ったことをスラスラと和歌にまとめあげられる器用さで「伝説」となった男です。
政治的には不遇な人生も、彼の横顔に陰りをプラスしていたのでしょう。モテるために生まれた男というような気がします。
平安時代初期の人物にもかかわらず、現代でも彼のモテはつづいているようです。
平安時代モノの創作物の常連キャラとして『うた恋い』やら『応天の門』などにぞくぞくと登場していますからね。
みなさんが高校などで古典の時間に習う、在原業平を主人公にした歌物語『伊勢物語』などもそうした歴史創作物の「祖先」ともいえるでしょう。
この在原業平……最後の歌とされる「つひに行く 道とはかねて聞きしかど 昨日今日とは 思はざりしを」の歌も『伊勢物語』からで、突然の病気に倒れた彼が「いつかは死ぬとは思っていたけど、それが昨日今日の問題として降って湧くなんて、思わなかったよ」という正直な気持ちが歌われています。
いろいろと恵まれて生まれた者特有の素直さがありますし、今回、次にご紹介する紀貫之などにくらべるとずいぶんと素直な人物だったのではないかと思われます。
『伊勢物語』にも、彼がどのように亡くなったかまでは描かれていませんが、「最後の歌」でも悟りっぽいことを言おうとしていない部分がナチュラルでよいと思われませんか?
享年55歳でした。
紀貫之

紀貫之 「手に結ぶ 水に宿れる 月影の あるかなきかの 世にこそありけれ」
『土佐日記』という物語の作者、あるいは『古今和歌集』の編者だったということで有名な紀貫之。
ただしこれは現代の学校教育の結果で、明治時代以前は、平安時代初期を代表する歌人として有名でした。
紀貫之の最期の歌は、言葉を補いながら意訳すれば「水を手に掬って、そこに写り込んだ月影のように、あるかないのかわからないような儚い人生でした」となります。
三十一文字しか使えない和歌という文学。
そこに、これほど深い思想を宿すことが出来るのか……さすがは名歌人ですね。
紀貫之が天慶八(870)年ごろ、一説に70代で亡くなろうとしているとき、病床から親友・源公忠(みなもとのきんただ)に書き送った「最後の歌」です。
この歌を送ってすぐに紀貫之は重態となり、その遺体は河原で焼かれて煙になってしまいました。
これだけ才能のある歌人だったのに、現代では歌人というより、むしろ物語作者・有名歌集の編集者として学校では教えられているのには理由があります。
明治時代の歌人・正岡子規に「紀貫之は下手な歌詠み」とケチョンケチョンにディスられてしまった過去があり、その正岡子規の影響力のほうが、学校教育的には「強い」わけですね。
それまでは無条件に尊敬されつづけていたというのに……。
しかも自分が国司として京の都から土佐に赴任した経験を描いた『土佐日記』では、なぜか主人公を女性ということにしたがゆえに、「ネカマ文学者」などといわれていたりします。
また男性に対して、めちゃくちゃ嫉妬心の強い男でした。
男性としての自分に自信がなかったのかもしれませんね。
紀貫之が猛烈にライバル視していたのが在原業平です。たぶん、なんでもスラスラと詠めてしまう在原業平が憎たらしいんでしょうか。
たしかに歌詠みとして両者の資質は真逆のように思われます。
『古今和歌集』の序文で、在原業平の歌を評して「その心あまりてことばたらず。しぼめる花の色なくてにほひ残れるがごとし」……意訳すると「自分のあふれる心を、言葉にする技量が足りていない。思ったことを歌にしてるだけだ。だから彼の歌は古いドライフラワーに香りだけが少し残ってるようなものにすぎない」と貶しています。
しかも貶していても、和歌集には在原の歌を相当数、入選させているという憎と愛が爆発しているタイプで、これはめんどくさい中年男性の典型だ~という印象が(個人的には)強いのでした。
在原業平と紀貫之、素の自分のままナチュラルに生きられる天才と、自分を否定し、克服したいタイプの天才とでは最後の歌にも大きな違いが出てくるようです。